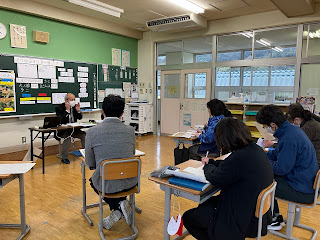「ブレンディッド・ラーニング」とは、オンデマンド受講(収録映像の視聴+SNS等による交流を含む)+オンライン交流+対面指導を組み合わせて実施する受講形態です。先生方を対象に、教職大学院の講義を体験受講できる機会となります。
「1講座=90分」×5回 を基本として、オンデマンド(個人での映像視聴受講)・学内による対面講義(半日程度)・オンライン(リアルタイムでの遠隔交流)を組み合わせて実施します。
全校種、全役職(教諭以外に講師や管理職も含む)が受講対象者です。本年度(2024年度)は試行期間を継続しており、無料で受講できます。
本年度のテーマ:「総合的な学習(探究)の時間」を再考する
次期学習指導要領の審議が行われている中、「探究的な学び」が主要なキーワードとなっています。また、総合的な学習の時間に「情報の領域」(小学校)の新設が提案されるなど、大規模な改変が予想されます。そこで、本年度のブレンディッド・ラーニング講座では、「総合的な学習(探究)の時間」を中心テーマとして設定しました。本講座にて、改めて「総合」を捉え直し、現状の抱える課題と今後の展望について学んで行きましょう。
開講期間:2025年 12月24日(水) ~ 2026年3月31日(火)まで
子供も先生もワクワクが続く!総合的な学習の時間〜持続可能な探究の授業づくり〜 | |
|---|---|
<講師名> 福永 徹 和歌山大学教職大学院 准教授 <プロフィール> 私立学校、日本人学校、和歌山市立学校で小・中・高等学校教諭として勤務し、保健体育科、社会科、生活科、総合的な学習の時間の授業づくりを研究。 その後、和歌山市教育委員会にて、教育行政、特別支援教育、学習指導、教育課程を担当。令和7年度より現職。教育方法学や教科教育学を中心に教師のICT活用指導行動が児童生徒の「深い学び」に与える影響等について研究を行っている。 <協力講師> 島本 和昌 和歌山市立広瀬小学校 校長 <プロフィール> 小学校教諭、指導主事、市内2校の校長を経て現職。 生活科・総合的な学習を中心に教師の指導技術と子供の見取りに卓越した経験を持つ実践家。「文部科学大臣優秀教員表彰」、「きのくに教育の匠」、「きのくに教育賞」受賞。 |
| 講座概要 | 総合的な学習の時間に「何から始めれば?」等の悩みを抱えていませんか?または、行事や学級活動の補充の時間になっていませんか?本講座は、その不安を「やれるかも!」という自信に変える具体的な方法をお伝えします。教育学の理論と現場で役立つ実践知を融合させ、「持続可能な探究の型」を習得。子どもが夢中になり、先生もワクワクできる授業づくりを目指します。講師や仲間と交流しながら、楽しく学びを深めましょう。 |
| 開講日程 | オンデマンド講義:1〜3講 12月25日(木)より配信開始 対面講義・第4~5講 2月8日(日)(13:10-16:20) 5回の講義は以下のような構成で行います。 第1講 探求的な学びの本質を捉え直す 第2講 総合的な学習の時間とカリキュラム・マネジメント 第3講 総合的な学習の時間において求められる授業改善と評価 第4講、第5講 協働と実践 ワークショップ |
| 受講対象 | 小学校が中心だが、中・高等学校も可 |
| 申込期限 | 2025年12月17日(水)まで 2025年12月19日(金)までお申し込みいただければ12/25の配信からご視聴いただけます(以後の申し込みは[冬季休業中を除き]随時受け付けますが、受講アカウントの発行に一定の時間がかかりますのでご了承下さい)。 |
社会科(歴史)から「総合へ」 | |
|---|---|
<講師名> 深澤 英雄 和歌山大学教育学部・非常勤講師 <プロフィール> 神戸市生まれ、神戸市内の中学校に1年、小学校に37年勤務し、和歌山大学教育学部教職大学院で特任教授を経て、現在非常勤講師。学力問題・授業研究・教師教育を実践研究しています。主な著書:『学習指導要領2020 実現のための「新・教師力20」』(小学館 2018) /監修:『ドラえもん社会ワールド なぜ? どうして? 日本の歴史』(小学館 2019) 他、学習関連書籍を多数執筆。 |
| 講座概要 | 児童・生徒が「おもしろい」「もっと知りたい」と思える社会科(歴史)授業がしたいという先生方!「教材研究のコツ」「新しい教科書研究のコツ」「授業構成のコツ」「授業展開のコツ」をテーマに授業改善の手立てを考えます。また、社会科は、児童生徒らの興味関心に基づいて「調べる・まとめる」活動が重要ですが、社会科から「総合的な学習の時間」への発展の仕方についても解説します。カリキュラムマネジメントや教科横断型の授業が注目されている中、社会科と「総合」の関係性、学習目的や授業方法の違いなどについても学んでいきましょう。 |
| 開講日程 | ●オンデマンド配信 第1講 12月24日(水)~配信開始 (2023年度の講座内容を再編集・再配信します。) ●オンデマンド配信 第2講 1月7日(水)~配信開始 (2024年度の講座内容を再編集・再配信します。) ●オンデマンド配信 第3講 1月28日(水)~配信開始 「社会科」から「総合的な学習の時間」への発展について 6年生の子どもが自分の興味をもった歴史上の人物の調べ学習(卒業論文の実践) ●対面講義 第4~5講 2026年2月末~3月中(13:10-16:20) 社会科6年歴史「ノルマントン号事件と条約改正」 (場所:和歌山大学にて実施) |
| 受講対象 | 主に小学校教員ですが中学校社会科教員も歓迎です |
| 申込期限 | 2025年12月17日(水)まで 2025年12月19日(金)までお申し込みいただければ12/24の配信からご視聴いただけます(以後の申し込みは[冬季休業中を除き]随時受け付けますが、受講アカウントの発行に一定の時間がかかりますのでご了承下さい)。 |
「総合的な学習の時間」における『情報の領域』 | |
|---|---|
<講師名> 豊田 充崇 和歌山大学教職大学院 教授 <プロフィール> 和歌山市で生まれ育ち県内中学校教諭を経て2002年度より和歌山大学教育学部に採用。専門は、教育工学・情報教育。ICT活用授業研究・情報モラル教育等。自ら「出前授業」を実施し「実践的研究」を生業としている。 |
| 講座概要 | 現在、中教審にて次期学習指導要領についての審議が行われており、小学校の「総合的な時間」に『情報の領域』が創設される見込みです。操作スキルや情報技術・情報モラル等について単発的に学ぶ「情報ブロック」、情報活用の実践力を育成する「ミニ探究ユニット」、そしてそれらを発揮していく「探究活動」といった配置イメージも具体化してきました。そこで、この『探究の領域』に相当する授業実践事例及び系統的なカリキュラムについて、先進校や県内の実例等を取り上げながら提案していきたいと思います。 |
| 開講日程 | オンデマンド講義:1〜3講 1月24日(土)より配信開始 対面講義orオンライン講義 いずれかを選択 第4講 2月13日(金)18:00~19:30 第5講 2月27日(金)18:00~19:30 |
| 受講対象 | 全教員 (管理職・教育委員会指導主事・ICT支援員の方なども受講いただけます) |
| 申込期限 | 2026年1月17日(土)まで |
「総合的な学習の時間」(高等学校向け)とSDGs | |
|---|---|
<講師名> 岡崎 裕 和歌山大学教職大学院 教授 <プロフィール> 在英日本人学校勤務の後、英国ヨーク大学、国際グローバル教育センター勤務。 帰国後は公立高等学校教諭を経てプール学院大学准教授 現在は和歌山大学教職大学院教授。 専門領域は、消費者教育、社会科教育、SDGs研究など |
| 講座概要 | まずは、「SDGsと学校」との関係をこれまでの経緯を踏まえながら解説し、「総合的な探究の時間」において、「SDGs」をどのように取り入れられているかについて、具体的な事例を紹介します(これまでの当講座を再配信いたします)。また、新規には高等学校でのSDGsに関する具体的な実例事案をもとに、総合的な探究の時間の現状・成果・展望について述べていきたいと思います。なお、これらの一連の講座を視聴いただき、希望者の方々には最終の質疑・応答の時間(最大90分)を設定させていただきます。 |
| 開講日程 | オンライン講義:希望の方々と日時調整の上実施 オンデマンド配信 第1講~5講 1月24日(土)から随時配信 |
| 受講対象 | 主に高等学校の教員を対象としていますが、他の校種の方々も受講できます。 |
| 申込期限 | 2026年1月17日(土)まで |
「総合的な学習の時間」指導の実際 | |
|---|---|
<講師名> 中川 靖彦 和歌山大学教職大学院 教授 <プロフィ―ル> 京都府内の中学校教諭、指導主事等を経て管理職。校長として総合的な学習の時間を中核とする「魅力ある学校づくり」を積極的に推進した。公認心理師・学校心理士SV 伊澤 真佐子 和歌山大学教職大学院 特任教授 <プロフィール> 平成元年度から26年間、和歌山市内の小学校教諭として勤務。その後、和歌山市教育委員会の専門教育監、和歌山大学教職大学院で教員育成のための業務に関わり、小学校長を経て現職。 山田 真稔
和歌山大学教職大学院 教授 <プロフィール> 公立小学校教諭、和歌山県教育委員会等、教育行政関係機関、小学校長を経て現職。理科教育、県下最小規模校校長の経験を生かした小規模校における教育実践等について研究している。 ※上記3人に加えて、豊田充崇も講師として1講座を担当します |
| 講座概要 | 大学生に「総合的な学習の時間」のこれまでの印象に」関するアンケートを実施したところ、「何を学んだか覚えていない」が大多数であり、本来の「総合」の趣旨と異なる授業を受けてきたという実態も明らかになってきました。一方で、探究的な学びが重視されている今、「総合」の重要性は増していることも確かです。 そこで、本学教育学部で実施されている「総合的な教育の時間の指導法」(教職必修)の講義担当職員によって、「総合」を最高する機会を設けたいと思います。 「総合」の本来の趣旨を踏まえて、その授業設計の工夫、児童らが主体的に学ぶための課題設定の方法、そして学びを菓子かするための評価方法などについて各教師の実践経験を踏まえて講義します。 今一度、「総合」を最高、再認識し、特色ある取り組み事例から、その学習法や成果について考えてみませんか。 ※当講座は各講師によるオムニバス形式の4つの講座を受講していただき、Q&A掲示板にて質問・意見・感想コメント等を受け付け、各講師から回答を行います。また、希望者には質疑の時間を設定させていただきます。 |
| 開講日程 | オンデマンド講義:第1講〜第4講 1月17日(土)より配信開始対面講義:Q&A掲示板に質問を受け付けしたり、希望者にはオンラインでの協議・質問時間を設定します。(対面講義日は設定いたしません) |
| 受講対象 | 小・中学校の教員及び指導主事など教育関係者全般 |
| 申込期限 | 2026年1月17日(土)まで |
講座申し込み方法(個人でご登録ください)
<申し込みフォームへ進めない場合>